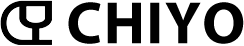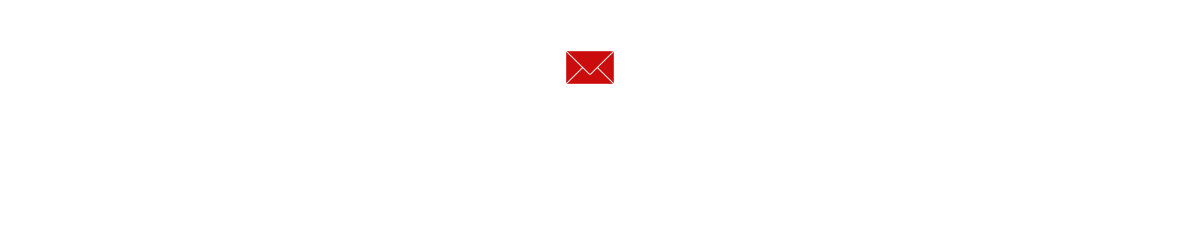飲食業は多くの人にとって身近なビジネスですが、共競争が激しく、時代の変化に左右されやすい業界でもあります。
だからこそ、「なんとなく」ではなく、明確な目的と方向性をもった経営戦略が必要です。
「企業の経営戦略」とは何か、飲食業における戦略の種類、策定の流れ、そして代表的なフレームワークを使った分析方法まで、実践的な視点で一般的な内容をご参照ください。
経営戦略とは何か
経営戦略とは、企業が中長期的な視点で、限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を、どのように活用し、どのような市場で、どのように勝ち抜いていくのかを
決定する指針の事です。
飲食店を例に挙げると、以下のような道標が必要です。
・どんな料理やサービスを、誰に向けるのか?
・価格帯は?立地は?営業時間は?
・競合店と、どのような差別化をするのか?
飲食業における経営戦略の主な種類
経営戦略は、さまざまな切り口で分類されますが、飲食業において特に重要な3つの基本戦略を紹介します。
1.コストリーダーシップ戦略(低価格戦略)
「安さ」で勝負する戦略です。原価を抑え、回転率を上げ、大量販売を目指します。
ex
牛丼チェーン、回転寿司、食べ放題業態など
ただし、利益率は低く、価格競争に陥りやすいため、規模の経済や効率化が不可欠です。
2.差別化戦略(こだわり・体験重視)
価格ではない、「独自の価値」で勝負する戦略です。
味・内装・サービス・ストーリー性などで他店と差別化します。
ex
オーガニック専門カフェ、完全予約の隠れ家レストラン、テーマ性のある飲食店などリピーターを生みやすく、価値もある程高める設定できます。
3.集中戦略(ニッチ戦略)
特定の地域、ジャンル、ターゲット層に特化する戦略です。
大手が参入しにくい領域で独自のポジションを築きます。
ex
駅前のサラリーマン向け立ち飲み、ビーガン専門弁当、子連れ専門カフェなど、少数でも熱烈なファンを獲得できれば、安定した経営が可能です。
経営戦略を立てるためのステップ
飲食業では経営戦略を策定するには、以下のプロセスを順番に踏むことが重要です。
ステップ1:現状分析(内部・外部環境)
まずは、お店の強み、弱み、業界の動向、競合の動きなどを把握します。
【フレームワーク】
SWOT分析、3C分析、PEST分析
※後述
ステップ2:目標設定
「どうなりたいか」を明確にします。
ex
・年商3,000万円を目指す
・月間来店数を500人に増やす
・UberEats売上を2倍にする
目標は具体的で測定可能なものが望ましいです。(SMART原則)
ステップ3:戦略の立案
ターゲット層、価格帯、商品構成、プロモーション方法、営業時間、立地などを総合的に考えます。
ex
・20代女性向けに、SNS映えするヘルシー丼専門店を展開
・近隣オフィスワーカー向け、炭火焼弁当を11~14時で販売
ステップ4:実行と検証(PDCA)
戦略は立てて終わりではなく、実行→結果を測定→改善点を見直し→再実行のサイクル(PDCA)を回すことで、現実に即した改善が可能になります。
飲食業に役立つフレームワーク
1.SWOT分析
S(Strength)強み:ex.炭火焼の技術、高いリピート率
W(Weakness)弱み:ex.英語対応不可、人手不足
O(Opportunity)機会:ex.外国人観光客の増加、空きスペースの有効活用
T(Threat)脅威:ex.近くに大手チェーン進出、原材料価格の高騰
自店の「立ち位置」と「伸びしろ」を把握するのに最適です。
2.3C分析
Company(自社):自分のお店の強み、特徴
Customer(顧客):誰が来るのか、何を求めているのか
Competitor(競合):近隣のライバル店は
3C分析は「どこで勝てるのか」を見極めるための道具です。
3.PEST分析
外部環境(自分では変えられない社会の流れ)を分析します。
P(政治):インボイス制度、感染症の規制など
E(経済):景気動向、物価上昇、最低賃金
S(社会):健康志向、働き方改革、ライフスタイルの変化
T(技術):モバイルオーダー、キャッシュレス決済、SNS活用し
「世の中の波」にうまく乗るには、PESTの視点が重要です。
経営戦略がないと、以下のようなデメリットが発生する可能性が考えられます。
・「なんとなく安くすれば売れる」と値下げ競争に巻き込まれる
・コンセプトが曖昧で、誰に向けた店か不明瞭になる
・売り上げ不振の原因が明確化できず、改善が困難になる
戦略を持つことで「売れない理由」ではなく「売るための理由」の明確化に繫がります。
店舗運営・スタッフ育成の関係
戦略は経営者だけのものではなく、現場と共有された、具体的な行動に落とし込まれてこそ意味があります。
ー経営戦略と運営戦略の連携ー
例えば、「高品質志向の差別化戦略」を掲げているのであれば、食材の選定基準、盛り付けのルール、接客スタイルなど、細部にまで戦略が反映されるべきです。
ースタッフ教育とモチベーション管理ー
経営戦略に合った人材育成も重要です。従業員が、お店の方針や価値観を理解して働けるように、定期的なミーティングやマニュアルの見直しを行うことが効果的です。
差別化のためのブランディング戦略
競争の激しい飲食業では、顧客に「また行きたい」「このお店が良い」と思ってもらえるブランド構築がカギになります。
ーブランドとは何かー
ブランドとは、単なる「ロゴ」や「名前」ではなく、「このお店は、こういう価値を提供してくれる」とお客様の心に形成されたイメージです。
・世界観の統一:メニュー、店舗デザイン、接客のトーンを統一させる
・ストーリーの活用:「なぜ、この料理を出すのか」「なぜ、この場所なのか」など背景を語る
・リピーター戦略:ポイントカードやSNS限定情報など、再来店を促す仕掛けを用意
これにより、価格競争ではなく「そのお店でなければならない理由」が生まれます。
デジタル活用による戦略強化
現代の飲食業において、デジタルツールの活用は欠かせません。
・SNSマーケティング:Instagram、TikTokで視覚的な魅力を発信
・モバイルオーダー/キャッシュレス:顧客利便性向上と人手不足対策
・データ分析:売れ筋や時間帯別売上から、戦略の見直しや販促計画へ活用
経営戦略を支える数値目標とKPI管理
KPIとは?
Key Performance Indicators:戦略が正しく機能しているかを示す具体的な指標です。
例えば、以下のような項目が飲食店のKPIにあたります。
| 戦略内容 | 目標 | KPIの例 |
|---|---|---|
| 高単価メニューへの誘導 | 客単価1,200円以上 | 高単価メニューの注文比率 |
| SNSを活用した集客 | フォロワー月間+300人 | Instagramの投稿と保存数 |
| ランチの回転率向上 | 1日30食販売 | 1時間あたりの来店数 |
「売上を上げる」「人気店になる」といった曖昧な目標ではなく、数値で測定できる目標を設定することで、スタッフとも共有しやすくなります。
また数値化することでPDCAが回ります。
戦略→行動→結果→改善というサイクル(PDCA)を機能させるためには、定期的にKPIを確認し、変化を追いかける仕組みが必要です。
そのため、一般的には以下のツールが活用されています。
・Googleスプレッドシート(簡易ダッシュボード)
・POSレジの月次レポート
・SNS分析ツール(Instagram Insight、Xアナリティクス)
無料で導入できるものも多くあります。
飲食業で成功するためには「味」や「立地」だけでなく、自店は「どこで」「だれに」「どのように」価値を届けるのかを明確にすることが重要です。
競争の激しい飲食業界だからこそ、「経営戦略」は生き残るための武器となるのです。
経営に正解はありませんが、「方向性」は必ずあります。
戦略を持ち、仮説を立て、試行・実行し、改善ーーーーーーーーーその積み重ねが、選ばれるお店作りの第一歩となるはずです。
経営戦略を立てる・または見直す際の一助となり、
今後、業務委託やパートナー選定の際に株式会社CHIYOを選んでいただけるキッカケとなれば幸いです。
是非お気軽にお問い合わせください。
https://www.chi-yo.jp/contents/category/contact/