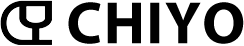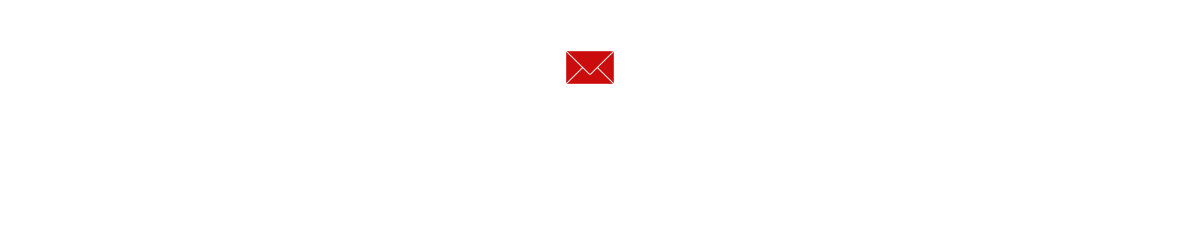近年、、製造業、IT、小売り、建設、不動産など多様な業種からの「飲食業参入」が加速しています。
背景にはコロナ渦を経た空きスペースの有効活用、フードデリバリー市場の拡大、インバウンド需要の回復といった経営環境の変化があります。
また現金商売ならではのキャッシュフローの速さや、ブランディング・クロスプロモーションへの可能性も大きな魅力です。
しかし、こうした表層的なメリットばかりに目を奪われてしまうと、事業としての継続性に欠け、数カ月で撤退に追い込まれるリスクも高まります。
飲食業は一見、参入障壁が低く見えて、実は極めて運営難易度の高い業態です。
異業種から飲食業へ参入する企業が直面しがちな落とし穴や失敗の要因を整理しながら、成功するための実践的な戦略設計と進め方の5つのステップに分けていきます。
なぜ「飲食業」へ参入するのか?
目的と位置づけの明確化がポイント
まず押さえておくべき前提として、飲食業は必ずしも利益率が高い業種ではありません。
営業利益率は平均で5~10%程度、原材料や人件費の高騰、衛生管理の厳格化、インボイス制度対応など、日常的に細やかなマネジメントが求められます。
それでも企業が飲食事業にチャレンジする理由は以下のような戦略的背景があるからです。
・キャッシュフローが早い
現金商売のため、売上から入金までのサイクルが短い。資金繰り改善や資金ショート対策に有効。
・ブランド認知の向上
飲食を通じて企業イメージを刷新、向上させる手段として活用可能。
・遊休資産の活用
本社ビルの1階や社有地、閉鎖予定の倉庫など、既存の固定資産を収益化。
・クロスセールスの起点
観光業、物販、ECなど他業種との相乗効果を狙える。
※飲食業はあくまでも「単独収益事業」としての成立だけでなく、会社戦略における位置づけの明確化が求められます。自社のビジネスモデルや既存事業との親和性、経営資源の分配可能性を見極めることがポイントです。
【STEP1】コンセプト設計と商圏分析
誰に・何を・どう提供するのか?
最初にすべきことは、明確なコンセプトとターゲット戦略の設計です。
ここが曖昧なまま進めると、後工程(商品設計・集客・収支)全てにブレが生じます。
➤コンセプト検討の3軸
- ターゲット層(例:オフィスワーカー、訪日外国人、住宅街の主婦)
- 商品軸(例:炭火焼肉弁当、低糖質ヴィーガンメニュー、地方食材専門)
- 提供スタイル(例:テイクアウト専門、店舗+デリバリー、無人販売)
例えば「平日昼のみ、オフィス街向け、日替わり弁当」のように、時間帯・立地・顧客特性を絞り込むことで、小資本でも勝ち筋を見出せます。
➤商圏調査の実施ポイント
- 商業地or住宅地/人の流れと時間帯の分析
- 周辺の競合店(品揃え・価格・客層)の把握
- 土日・平日、昼・夜の人通り
- 建築用途(オフィス・学校・ホテル・住居など)の分布
可能であれば、1週間以上の現地観察を行い、体感で「立地ポテンシャル」を掴む事が大切です。
【STEP2】資金計画と収支シミュレーション
飲食業は「初期投資が少なくて済む」と誤認されがちですが、厨房設備・内装・許認可・広報費などで一般的には300万円~800万円のコストは見込まれています。
➤主な初期コスト内訳
- 内装・厨房機器購入またはリース
- 給排水・電気・ガス工事(業態により異なる)
- 什器・備品・レジ端末
- 保健所申請や消防対応
- 看板・WEBサイト・SNS運用
- 原材料仕入れ・試作費用
さらに「開業後3カ月の運転資金(家賃+人件費+原価+販管費)」として、最低でも月商の3倍程度を別途準備しておくことが安全とされています。
➤損益分岐点を把握
- 月商に対する原価率、人件費率、販売管理費率を明確に
- 売上目標に応じた日販ベースのKPI設定(ex.1日50食×単価850円=42,500円)
収支シミュレーションを作成し、複数のシナリオ(楽観、現実、悲観)を検討するのが良いです。
【STEP3】許認可と法令対応
飲食業を始める際には、複数の行政手続きが必要です。
➤必須となる主な届出・許認可
- 飲食店営業許可(保健所)
- 食品衛生責任者(資格受講)
- 防火管理者(一定基準以上)
- 開業届(税務署)
- インボイス登録(課税事業者の場合)
加えて2021年から完全義務化されたHACCP(衛生管理計画)対応も求められます。
衛生マニュアルの整備、記録簿の運用、定期 点検体制の確立など、ルームベースで構築します。
【STEP4】人材採用と教育
飲食店は、料理や立地以上に「スタッフの対応」で評価が分かれます。いわば「人の業」。
飲食店の仕事が単なる作業ではなく、人との関わりや、お客様の心を豊かにする行為である事を意味します。
具体的には、お客様にお食事を提供するだけではなく、その時間や空間を演出することで、喜びや安らぎを与え、
時には特別な思い出を創り出す役割を担うことを指します。
➤人材の3つの確保パターン
- 自社社員の異動(教育と意識転換が必須)
- 飲食経験者を外部から雇用(人件費高)
運営を外部に委託(コストとリスクのバランス)
➤教育と評価制度の整備
- 接客・レジ対応・盛り付け・清掃などのオペレーションマニュアルを標準化
- 衛生研修(ノロウイルス、アレルゲン、異物混入)
- スタッフごとの目標管理・評価・フィードバック体制
離職率の高い飲食業界だからこそ「働きやすさ」「裁量」「キャリアパス」を整えることが継続経営の前提となります。
【STEP5】スモールスタートと市場検証
最もリスクを抑えられる方法は小さく始めて、うまくいった部分を拡大していくことです。
➤テスト施策の具体例
- 平日ランチタイム限定のお弁当販売(場所:自社敷地、ポップアップ)
- 近隣企業・住民向けの試食会(アンケート回収)
- 商業イベントの短期出店(出張型)
数値目標を「売上」だけでなく「リピート率」「SNS反応率」「フードロス率」などにも設定し、データから改善のヒントを抽出しましょう。
一般的に現場で頻発する課題と改善のFAQ
Q1.利益が安定せず、赤字が続いている
対策
単なる売上不足ではなく、「収益構造の見直し」が必要です。
特に原価率、人件費率、設備償却費、販管費など、固定費と変動費のバランスを分析。
併せて、以下の観点で経営数値を可視化し、改善サイクルを回すことが重要です。
・廃棄、ロスの発生状況と抑制策
・メニューごとの利益率(収益貢献度)
・在庫回転率と発注精度
・値引きやキャンペーン施策の費用対効果
これらを月次でモニタリングし、改善案を志向、検証、定着させるPDCA体制を構築。
Q2.スタッフの離職が早く、人材が定着しない
対策
採用難の時代において「給与水準を引き上げる」だけだは定着率は改善しません。
離職の原因には以下のようには以下のような離職環境の構造的課題が潜んでいます。
・教育不足による業務ストレス
・シフト運営の不公平感
・成長実感や評価制度の欠如
・オーナー、管理者との信頼関係の希薄さ
したがって、定着率を高めるには「働く理由」を提供できる組織作りが必要です。
ex
・業務フローのマニュアルの明文化による負荷軽減
・社内コミュニケーションや1on1ミーティングの導入
・スタッフ表彰制度や昇給基準の明確化
・ワークライフバランスを考慮した勤務シフト設計
離職はコストであり、スタッフの定着=店舗運営の安定性と認識すべきです。
Q3.SNSでの集客がうまくいかない
対策
SNSは「無料の広告媒体」と捉えがちですが、実際は継続的に「戦略的なコンテンツ設計と運用」が必要なプロモーション活動です。
集客効果が出ない理由の多くは以下にあります。
- 商品やブランドの「ストーリー」が伝わっていない
- 投稿頻度や時間帯が不規則
- 写真や動画が訴求力に欠けている
- 「誰に向けた情報なのか」が曖昧
改善のためには、投稿の目的(認知・来店・再訪)とターゲットを明確化し、以下のような運用体制を整えましょう。
・コンテンツカレンダーによる計画的投稿
・顧客インサイトを反映した内容設計(例:裏側投稿、店主の声)
・撮影のプロやSNS運用代行の一時的な活用
・店舗スタッフを巻き込んだ投稿企画(UGC施策)
SNS集客は「運用の質と継続」が成果を分ける鍵です。
継続的な成長を支える”マインドセット”と”組織構造”
飲食ビジネスを安定的かつ持続的に成長させるには、属人的な運営から脱却し、「構造として回る仕組み化」が不可欠です。
以下の観点を事業の根幹に据えることで、拡大や多店舗展開にも耐えうる事業体制が築けます。
■再現性のある運営モデルの構築
個人の力量に頼らず、マニュアル・KPI・定例ミーティングなどを通じて誰がやっても一定の品質が保たれる設計にすることが大前提です。
■データに基づいた経営判断
勘や経験則ではなく、POSや原価計算ソフトを活用した数値主義の経営を意識。
店舗ごとのPL分析やメニュー別貢献度の可視化も必要です。
■初年度は「学習と改善」のフェーズと割り切る
初年度は、黒字よりも「オペレーション確立と需要の確認」が主目的。
焦って投資拡大するより、ミニマムでの検証と修正を繰り返すスタンスが肝要です。
■現場責任者の役割設計と裁量
店舗責任者には明確な目標(売上・CS・改善提案など)と裁量権限を与え、オーナーの”代理人”としての育成を意識。
短期の数値だけでなく、育成・マネジメント力も評価項目に加えましょう。
飲食業はシンプルに見えて、実は非常に奥深い事業です。
だからこそ、異業種の企業が参入することで新たな視点や革新が生まれ、業態全体が活性化する可能性も秘めています。
しかし、その一方で成功のためには「属人的な経験」ではなく、「再現性ある構造」と「数値に基づいた判断」、そして「継続可能な仕組みづくり」が不可欠です。
短期的な利益を求めるのではなく、数年単位で事業として育てていく視点が重要です。
飲食事業は、日々の小さな積み重ねがブランドとなり、信頼となり、やがて事業の柱となります。
「食」は時代が変わっても人々の生活から決してなくならない領域です。
だからこそ、綿密な準備と明確なビジョンをもって、一歩ずつ丁寧に積み上げていくこと。
それが、飲食業を”事業”として成功させるための第一歩です。
飲食業に新たな可能性を見出し、挑戦する企業様のお手伝いが出来たら幸いです。
是非、お気軽にお問い合わせください。
https://www.chi-yo.jp/contents/category/contact/